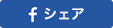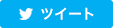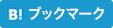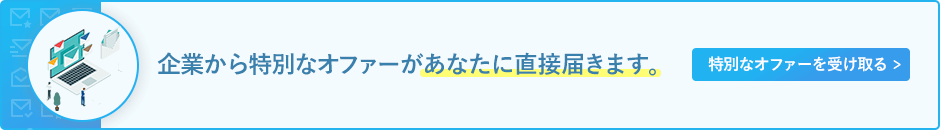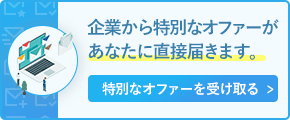人気の居酒屋フランチャイズチェーン、本部選びのコツと成功の秘訣とは
安定した需要があり、身近な存在であるといえる飲食店は、独立開業において人気の業態のひとつ。しかし、食材費をコントロールしづらく、席数によって売上の上限が決まるため、利益を出すことが難しいのも事実です。安定した経営を目指し、フランチャイズチェーン(以下、フランチャイズ)への加盟を検討している方も多いのではないでしょうか。
飲食店といってもさまざまですが、今回は飲食不況のなかでも本部の数が増え続けているという「居酒屋」をピックアップ。多くの選択肢があるなかで、どのような点に注意して加盟を検討すればいいのでしょうか。飲食店コンサルタントとして、新店舗開発支援や集客力向上支援などを行う金子敦彦さんに、近年の業界事情とともに教えていただきました。

<INDEX>
スマホの普及が居酒屋業界に大きな影響を与えていた

──居酒屋業界全体の市場動向や近年の傾向について、教えていただけますか?
金子:全体の売上は、1992年の約1兆4,000億円(日本フードサービス協会「外食産業市場動向調査」)をピークに減少傾向にあり、2016年は約1兆円。そのなかで、フランチャイズは約4,000億円(「JFAフランチャイズチェーン統計調査」)を売り上げています。フランチャイズの売上も市場全体に合わせて減少傾向にありますが、本部の数は右肩上がりで増えていますね。
──それはなぜでしょうか?
金子:もともと、店に入ってみなければ値段も雰囲気も味もわからない飲食業は、「入店までのハードルが高い」業界といわれていました。小売業なら気に入らなければなにも買わずに帰ることができますが、飲食業は店に入ったら基本的に消費しなければならないですからね。
そういった背景があるなかで、総合居酒屋といわれる大手フランチャイズは、メニューの種類が豊富で安価かつ、お客さまが安心して入店できたため、1990年代から2000年代前半にかけて、人気が集中したんです。最近はスマートフォンの普及などによって、さらにお客さまの利用動向が変わってきています。
──たしかに、スマートフォンが普及したことで、お店を事前に調べられるようになりましたよね。その結果、本部の数が増えているということですか?
金子:食べたいものを検索して店を選ばれる方が多いので、総合居酒屋よりも専門店の需要が伸びています。その需要をうまく捉え、「串カツ」や「焼き鳥」など、分野に特化した新興の本部が勢いを伸ばしているため、本部の数は増え続けているんです。細分化が進んでいるということですね。
また、総合居酒屋のシェア増大とともに進んでいた低価格化にも変化を与えています。料理へのこだわりやお店の雰囲気などもすぐに知ることができますから、客単価が高くても、それに見合った魅力があればお客さまに来ていただけるようになってきていますね。
仕組みが確立された老舗か、いまのニーズを捉えた新興勢力か。
本部選びのジレンマ

──お店の情報を調べやすくなったことで、個人店が知ってもらえるチャンスも増えていると思うのですが、そのなかであえてフランチャイズに加盟するメリットは?
金子:たしかに、個人店でも戦える時代になっています。とくに居酒屋は身近なので個人で始める方も多いのですが、利益を上げるノウハウを学ぶことが難しい業態でもあります。ですから、ビジネスモデルができあがっているフランチャイズの仕組みを手に入れられるということは、大きなメリットだと思います。
売上に対して食材費が30%、人件費が25%、家賃を10%以内に抑えるのが、健全な経営のための目安といわれています。このなかで、食材費はコントロールするのがとても難しく、個人開業だと、50%を超えている場合も珍しくない。家賃は変動させられませんから、結果的に人件費にしわ寄せがきて、自分の給料を出すことができないケースも多いんです。
その点、フランチャイズであればメニューも決まっていて、本部が一括して大量に仕入れているため、価格を安定させることができます。その意味で、本部が仕入れルートをしっかりと確保しているかは、本部選びで非常に重要なポイントになると思います。
──なるほど。仕入れ以外では、本部を選ぶ際にどんなポイントを見ることが大切でしょうか?
金子:当然ですが、店舗数や営業年数といった実績ですね。ビジネスモデルができており、そのノウハウを得られることがフランチャイズ加盟のメリットだと言いましたが、新興本部のなかにはそういった仕組みが未成熟なところも見受けられます。
個人店でも戦える時代になったこともあり、大手フランチャイズの看板をつけることはマイナスイメージにつながると考える人もいますが、基盤がしっかりしている本部はマニュアルも、サポート体制もしっかり整備されている。仕入れに関してもそうですが、フランチャイズは多くの店を展開しているからこそ、より機能するともいえますからね。
──基本的には老舗のほうが、さまざまな面でメリットがあるのでしょうか。
金子:いえ、安定感としては老舗の本部だと思いますが、大規模な本部は小回りが利きにくいという側面もあります。お客さまから魅力的に思ってもらう意味では、いまのニーズに合わせて生まれた新興本部が強いんです。そのジレンマに対して、いかに答えを出すかが大切だと思います。
新興本部のなかには、単に流行に乗っているだけの本部もあるので、料理の味や店自体の魅力といった本質的な部分を見たほうがいい。実際に営業している店舗に行って、自分で確かめることをおすすめします。
家賃と売上のバランスが大切な立地選び。
売上予想には「坪売上」が重要

──初期費用の目安について、教えてください。
金子:物件取得費用の割合が大きく、サイズや立地によってバラバラですが、2,000万円くらいは見ておいたほうがいいと思います。
かつては宴会需要を取るために広い店舗が必要だったのですが、近年では20坪、40席ほどの小型店も増えてきて、初期費用は少しずつ下がってきています。とはいえ、安い金額とはいえないですけどね。内訳は、ある居酒屋チェーンが公開しているシミューレションによると、内装を含めた物件取得費に1,000万円、加盟金や設備投資に900万円ほど。もちろん、坪単価などによって変動します。
──それだけの金額となると、融資を受けることも念頭に置いておくべきかもしれませんね。
金子:そうですね。初期費用の3分の1程度を自己資金で用意し、それ以外は融資を受ける方が多いように感じます。融資を受けるためにはしっかりとした事業計画書が必要なのですが、フランチャイズの場合、ほかの店舗のデータなど、計画書に載せる根拠を提示しやすいでしょう。また、ビジネスモデルができているので、融資を審査する担当者の印象も、個人開業とは違うはずです。
──運転資金を余分に残しておいたほうがいいとよくいわれますが、それは居酒屋でも同じでしょうか?
金子:もちろん、それは残しておいたほうがいいでしょう。理想をいえば人件費や家賃などを6か月間支払えるくらいの余裕がほしいですが、フランチャイズの飲食店は、売上の初動が速いことも特徴のひとつ。最低3か月分の資金を残す、というのが目安だと思います。
──フランチャイズの飲食店は、開店当初から結果を出しやすいのですか?
金子:というよりは、結果を出さなければいけないですよね。ほかの地域で人気の店が、ここにもできましたとオープンするわけですから。もちろんすぐに利益を出すことは難しいですが、個人店に比べたら速い傾向です。
──立地選びで気をつけたほうがいいことはありますか?
金子:駅前がいいのか、ロードサイドがいいのかなど、業態の特徴によって向き不向きがあるので、本部と相談しながら、条件が似ている店のデータも参考にして選んだほうがいいと思います。すでに自分で物件を持っている場合は、似たような立地で利益を出している本部を選ぶ、という方法もあるでしょうね。
──家賃は売上の10%以内に抑えるというお話がありましたが、立地選びではそのバランスも重要になるわけですよね。
金子:もちろんです。ただし、居酒屋に限らず飲食店では、店の広さや席数がそれぞれ異なるため、立地条件が似ていても、ほかの店舗の総売上と比較することは難しい。そこで、1坪で月にいくら売り上げられるかを示した「坪売上」という指標が重要になります。
一般的に居酒屋では、平均値が1坪15万円程度、30万円を超えるとかなりの繁盛店といわれています。同じ本部、かつ似た立地で営業している店舗の坪売上を参考に売上予想を立て、家賃との比率を考えることが大切となるでしょう。
──実際に開業後、運営していくうえで気をつけたほうがいいことはありますか?
金子:従業員のマネジメントですね。とくに深夜営業も多い居酒屋では問題となることも多いです。しっかりとした就業規則をつくったり、負担を減らすためにオペレーションを改善したり、労働環境に気を配ることは重要だと思います。本部選定のうえで重要視するべきポイントでもあるのですが、実際に人を雇うのはオーナー。重大な責任が伴うので、労働基準法の理解は必要です。
──フランチャイズ運営で重要となる、多店舗展開についてはいかがでしょうか?
金子:初期費用も大きいですし、スタッフ育成などさまざまな問題はありますが、基本的には複数店舗をやらないと利益を伸ばせない業態だといえます。席数が決まっている以上、売上を青天井で増やしていくことはできないですからね。はじめから、次の店舗の店長候補を育成する意識は持っていたほうがいいでしょう。
1店舗目と近いエリアに出店する「ドミナント方式」であれば、スタッフや食材の融通という部分で大きなメリットがあります。1店舗目で得たノウハウを活かせるので、労力は2店目のほうが少なくて済むと思いますよ。
居酒屋は、お客さまとの「コミュニケーション」の工夫によって単価を上げられる

──フランチャイズの居酒屋に加盟し、成功するために必要な素養を教えてください。
金子:リーダーシップが重要だと思いますね。仕組みやマニュアルができているフランチャイズでは、調理や仕入れに関しては未経験者でもできるようになっている。実際にスタッフを動かしていくための、現場での統率力が必要になります。
──料理が得意とか、接客がうまいといった要素は関係ない?
金子:もちろん、そういったスキルを持っているに越したことはないですが、現場のオペレーションが長けているプレイヤーがオーナーに向いているかというと、必ずしもそうではないと思います。ちゃんと本部とコミュニケーションを取れるとか、アルバイトをまとめあげる力のほうが大事。むしろ料理人の場合は、料理へのこだわりがあると思いますので、本部がメニュー構成を決めるフランチャイズには向かないかもしれません。
──今後、フランチャイズの居酒屋ではどのような点が重要になるでしょうか?
金子:個人的には「省力化」が鍵を握ると考えています。人口減だけでなく、労働環境が悪いイメージもあり、飲食業は人材不足が深刻な問題。しかし、人件費率が高くなるとフランチャイズの収支モデルが崩れてしまうので、単純に給料を上げれば解決するという問題ではないんです。
だから今後は、人が少なくても運営できる店舗や、人材採用のノウハウ、人を定着させる仕組みを持った本部が強さを見せるのではないでしょうか。福利厚生を充実させたり、働きやすい就業規則を指導したり、そういったテコ入れをするところが増えると思います。
──お客さまに対しての面ではいかがですか?
金子:最近は他業態の店による「ちょい飲み」が増えており、居酒屋とそれ以外の業態のボーダレス化が進んでいます。また、コンビニやスーパーの惣菜や冷凍食品を買って、家でお酒と一緒に楽しむ「中食」も定着していますよね。そんな状況のなかで、わざわざ店に来てもらい、外食する価値を高めていかなければならないと思っています。
たとえば、いま「浜焼き」など、お客さま自身が調理を行う店が流行しています。昔からある形態ですが、エンターテイメントとして見せつつ、省力化につなげるという方法は、今後の大きなヒントになるのではないでしょうか。
また、先ほども話したとおり売上に上限があるので、それを補う外販商品や持ち帰り商品を充実させることも、活路になると思います。
──他業態からもライバルが出てきているんですね。では、居酒屋の強みはどこにあるのでしょうか?
金子:ほかの飲食店と比べても、居酒屋はお客さまとのコミュニケーションが重要な業態であり、それこそが強みだと思います。たとえば牛丼屋だったら、基本的にはお客さまとのコミュニケーションは会計時しかないですが、居酒屋は違います。コミュニケーションを積み重ねることで、客単価を上げることもできます。
それは接客に限った話ではなく、貼り紙やメニューも、広い意味ではお客さまとのコミュニケーションといえます。そういった部分に工夫の余地があり、売上に直結するという点で、居酒屋はやりがいのある仕事だといえるのではないでしょうか。

金子 敦彦
経営コンサルタント/中小企業診断士。飲食店でのフロアマネジメント、小売フランチャイズチェーンでの販売員指導およびマーチャンダイジングなどを経験後、独立。年間500回以上の経営支援・コンサルティングを行っている。専門分野は飲食店支援をはじめとするフードビジネスコンサルティング。中小企業診断士金子敦彦事務所代表。フランチャイズ研究会会員。日本フランチャイズ研究機構(JFRI)所属。