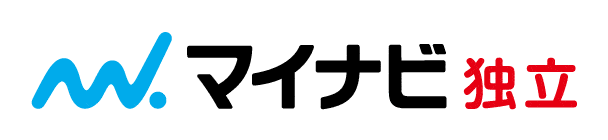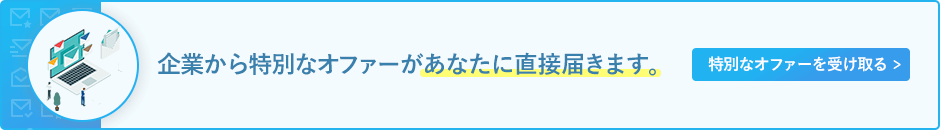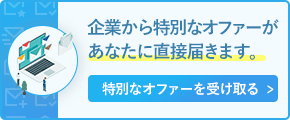身近な起業成功例も紹介!起業で成功するためのポイントとは?
コロナ禍を経て就業環境が大きく変わる中、キャリアの選択肢として独立・起業を視野に入れ始めた方もいるのではないでしょうか。起業するからには「失敗したくない」「成功したい」という気持ちはあるものの、どうすれば良いのかわからない…。きっと、そんな不安や悩みをお持ちの方も多いはずです。この記事では、起業成功のヒントとなる情報として、起業を成功させるためのポイントや起業アイデアの見つけ方、身近な起業家の成功事例などをご紹介します。
<INDEX>
「起業成功」の基準とは?
「成功した起業家」と聞いて、多くの人がイメージするのは「経済的に成功を収めた人」、平たく言うと「お金持ち」ではないでしょうか。しかし、大きな利益や収入を得ることだけが、起業成功の基準ではありません。起業する目的は人それぞれです。事業において重視するポイントも人によって異なります。経済的な成功を目指す人もいれば、社会貢献や自己実現などに重点を置く人も少なくありません。そうした起業の目的や事業ビジョンを実現することが、すべての人にとって「起業が成功した」と言える基準であり、その状態が長く持続するほど、より大きな成功と言えるでしょう。
起業を成功させるための3つのポイント

では、起業を成功するためには、どのような準備や心構えが必要なのでしょうか。3つのポイントをご紹介します。
起業の目的を明確にする
先述の通り、起業の成功とは「起業の目的を達成すること」です。つまり、起業の目的が明確になければ、成功することはできません。起業を成功させるために、まずは「なぜ、起業するのか」という理由を自問し、突き詰めて考えることが重要です。起業することで、どんな自分になりたいのか、どんな生活をしたいのか、社会に何を提供したいのか。自分が実現したいこと(=目的)をしっかりと設定し、優先順位を決めることが、起業の第一歩と言えます。このとき、「社会的に立派な目的」を取り繕っても、それが「本当に自分が実現したいこと」でなければ意味がありません。起業目的は成功への指針となる大切なものだからこそ、建前ではなく本音で考えるようにしましょう。
人とのつながりを大切にする
起業すると、取引先などの顧客開拓をはじめ、あらゆる業務を自分自身で判断・実行しなくてはいけません。ときには一人では解決が難しい問題に直面することもあります。何かしら困ったときに、大きな助けになるのが人脈やコネクションです。人に相談したり、頼ることで自分では思いつかない解決策や選択肢を提示してもらえることがあります。人とのつながりを大切にし、知り合いの輪を広げる努力をすることによって、起業成功の可能性が高まります。
小さく始める
起業する目的や事業ビジョンにもよりますが、一般的には小さな規模から事業をスタートし、段階的に大きくしていく方法のほうが短期間で失敗するリスクを抑えることができます。最初から大規模な投資を行い、事業が軌道に乗るまでに想定以上の時間がかかった場合、目的を達成する前に資金がなくなり、事業を立て直すことが困難になる可能性があります。成功確率を上げるためには、スモールスタートから取り組むことが重要です。
起業アイデアの見つけ方
起業しようと思ったときに、大きな壁となるのが「どんな事業を始めれば良いのか」という具体的なビジネスプランを考えることだと思います。選択肢が広い分、「アイデアが思いつかない」「どう考えれば良いのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。また、「独創的で斬新なものでないと成功できない」という思い込みが自由な発想を妨げてしまうこともあります。
ビジネスプランを考えるときは、まずはさまざまな角度からアイデアを出してみることが大切です。そのうえで、「現実的に実現できるか」「自分の起業目的に合っているか」という視点で、絞り込んでいくと良いでしょう。市場のニーズが見込めるアイデアであれば、決して革新的なものでなくても構いません。ここでは、幅広くビジネプランを考える際に役立つ切り口をいくつかご紹介します。
自分の経験・スキル・得意分野から発想する
まずは、シンプルに「自分ができること」「得意なこと」を棚卸しして、その強みを活かしてどんなことができるのか考えてみましょう。自分の考えだけでなく、同僚や友人など第三者の意見を参考にするのも有効です。
- ●営業代行業(営業経験を活かした既存商材を扱う営業特化事業)
- ●コンサルティング(自分の専門知識や経験を活かせる領域でのコンサルティングサービス)
- ●子育て支援サービス(子育て経験を活かした子育て支援のWebサイトやイベント運営事業)
「困った」「不便だな」という体験を参考にする
仕事や日常生活の中で「困った」「不便」「面倒くさい」と感じることは、少なからず誰にでもあるはずです。そうした「課題」を解決する方法を考えることが、新しいビジネスモデルにつながる可能性もあります。自分だけでなく、身近な人の体験談を聞いてみるのも良いでしょう。
- ●家具組み立て代行サービス(家具の組み立てが面倒な人に向けて組立スタッフを派遣するサービス)
- ●トイレットペーパーサブスクリプション(買い忘れを防ぐサブスクリプションサービス)
- ●ペットの散歩代行アプリ(ペットの散歩ができないときに代行してくれる人を探せるアプリ)
既存サービスの改良点を考えてみる
普段、自分が利用しているサービスに関して「どうすればもっと便利になるか?」という視点で考えるのも有効な方法です。既存サービスを改良したり、他のサービスと組み合わせることで、新しいサービスが生まれるかもしれません。
- ●フィットネスアプリと食事宅配サービスの連携(アプリのデータにも基づく食事の宅配サービス)
- ●音楽アプリとチケットサービスの連携(音楽アプリを通じてライブチケットを販売するサービス)
- ●ファイナンシャルプランニングができる結婚アドバイザー(結婚後の生活も支援するサービス)
成功事例を手本にする
国内で広く成功しているビジネスや海外で成功している事例を手本として、起業に活かす方法もあります。フランチャイズの加盟店や代理店として利用契約や販売契約を結んで活用するケースのほか、既存のモデルをアレンジして新しいサービスとして展開することも可能です。
- ●有名商材の販売代理店(他社が開発した商材の販売を行う代理店事業)
- ●クリーニング受取・配送代行(飲食店の配送代行ビジネスをクリーニングサービスに応用した事業)
- ●軽トラックシェアサービス(軽トラックに特化したカーシェアリングサービス)
起業アイデアが浮かばない方には、こんな方法も
一言に起業といっても様々な方法がありますが、起業アイデアを起点にした起業が難しいと感じる人は、以下のような方法もあります。
フランチャイズ
フランチャイズ本部が培ってきた運営ノウハウやブランド力(商品の魅力)を活用し、自分自身が経営者(オーナー)となる代わりに、加盟金やロイヤリティ(売上の一部)を企業に支払う経営方法です。
業務委託
委託元である企業と契約を結び、特定の業務を請け負い、報酬を支払ってもらう働き方です。自分の得意分野を仕事にでき、時間に縛られることなく働くことができます。
代理店
売主やメーカーの商品・サービスを代理で販売できる契約形態です。売価から卸値(マージン)や手数料(フィー)を引いた金額が、代理店の報酬となります。低リスクですぐに販売できることが魅力です。
独立候補社員
契約社員あるいは正社員として働き、その後、社内の独立支援制度等を活用し「フランチャイズ」や「のれん分け」等で独立する開業方法です。収入を安定させながら、自身の適性を確認することができます。
身近な起業成功事例
先人の成功事例に学ぶのは、起業を成功に導く上で非常に効果的な方法です。さまざまな事業で成功を収めている先輩起業家たちの体験談を見てみましょう。
HOLUDONA代表 和田美香さん

和田美香さんが代表を務めるHOLUDON株式会社では、親子の移動をサポートする雨具作りをメイン事業として手がけています。子どもの通学用雨具と、大人の自転車用雨具の2種類をKAPAPA(かっぱっぱ)シリーズとして展開。子どもの通学用雨具は、ランドセルの上に取り付けられるポーチにレインコートを入れておくことで、雨が降ってきてもすぐに着られるように工夫されています。和田さんは、どんなアイデアから商品を開発したのか、どのように事業を軌道に乗せたのか、体験談を見ていきましょう。
わが子の一言からKAPAPAを発明
KAPAPAを発明したのは、現在、20歳になる長男が、小学校1年生になったばかりのときです。通学や遠足にレインコートを持っていくのですが、雨が降っても着ないで濡れて帰ってくることが続きました。「レインコートを持っているのに、なぜ着ないの?」と聞くと、「面倒だから着たくない」と言われました。どうやらランドセルの上から着られないし、そもそも出し入れが手間とのことでした。これはなんとかしないといけないと思い、自分で息子が着たくなるようなものを作ってみようと考えました。
成功の秘訣は、起業前に「応援してくれる人」を見つけること
思いついたアイデアやサービスを形作るのは本当に楽しいし、やりがいもあります。だけども、やはり現実として、自分で会社を起こして、さらに経営していくことは大変でもあります。だからこそ、起業前にできるだけ経験を積んだり、応援してくれる人を見つけたりと、準備をしてから臨んだほうがより失敗が少なく、スムーズに事業を進められると思います。
(応援してくれる人たちを見つけるために)私の場合、ものづくりをしている人のセミナーや、今だとオンラインサロンに入って、情報を集めています。自分がやりたいことをやっている人の話は本当に参考になりますから。そしてもう一つ、とにかく自分がやりたいことを発信する。そうすると、共感してくれた人からアドバイスをもらえるし、話すことで自分の考えも整理できます。以前、関係がなさそうだと思っていた人に事業アイデアを話していたら、のちに応援者となってくれる人とつなげてくれたこともありました。どこでどんなご縁があるかわかりません。どんどん発信してみてくださいね!
和田さんの事例は、身近な「困った」「不便だな」という体験から起業のアイデアが生まれ、成功したケースです。つい商品のアイデアだけに目が行きがちですが、事業を軌道に乗せるためには、セミナーやサロンに参加したり、自ら情報を発信することによって、人脈を広げることが重要なポイントであると言えます。
イチロウ株式会社代表 水野友喜さん

愛知県と一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)で、訪問介護サービス「イチロウ」を提供しているイチロウ株式会社の代表・水野友喜さん。イチロウは介護保険制度を利用しない保険外(自費)の訪問介護サービスで、あらゆる介護・生活支援を好きな時、好きな時間受けることが可能。プロの介護士をいつでもすぐに自宅まで派遣できる点も大きな特徴です。そんなイチロウはどのようにして生まれたのか、水野さんの体験談をご紹介します。
介護問題の本質に切り込んでいくことが大事だと思い、イチロウを考案
元々は介護士として現場で5年、管理職として5年勤務した後、老人ホーム紹介業と、居宅介護支援事業の2つの事業で起業をしたのですが、株式会社を立ち上げるだけで資金をすべて使い切ってしまった苦い思い出があります。縁があり、老人ホームのコンサル業を始めてから、売上として月次で100万円を超えるようにはなったものの、結局、介護業界の課題を解決するような事業ではないと思い始めました。もっと業界が変わるような、ダイナミックなビジネスを作りたいと考え、未上場企業や起業家向けの支援プログラム「アクセラレータープログラム」を受けることにしました。その中で、メンターの一人から「介護士が良い収入を得る仕組みを作ることに挑戦すべきなのでは?」と言われ、はっとしました。それで、介護問題の本質に切り込んでいくことがスタートアップとして大事だと思い、イチロウを考案しました。
清水の舞台ほどの高さもなければ、意外とうまく着地できるのが起業
起業する前は、清水の舞台から飛び降りるぐらいの覚悟をしていました。ただ、実際に飛び降りてみると、すぐに足場があり、なんとかなったという感じです。この例えはある起業家がされていたのですが、本当にその通りで、すぐ階段があるようなイメージです。何か始めたいなら勢いも必要です。二の足を踏んでいるなら、ぜひ飛び込んでみることをおすすめします。
イチロウは水野さんの介護業界での経験に基づき、既存サービスの課題に向き合うことで生まれたサービスです。介護の現場に深く通じているからこそ考案できた社会のニーズに適うサービスと言えます。また、思い切って起業に挑戦した結果、「なんとかなった」のも、自身の専門性を発揮できる分野で起業したことが大きな要因と考えられます。
株式会社ブルーコンパス代表 蜂谷詠子さん

2015年に法人化した株式会社BEEVALLEYと、2018年設立の株式会社ブルーコンパス、2つの会社の代表を務めている蜂谷詠子さん。BEEVALLEYでは 女性起業家を対象にしたWeb制作事業を展開。ブルーコンパスでは女性専用のコワーキングスペースの運営をメインに、女性の起業支援や小学生から高校生までを対象にした女子専用学習塾の経営などを展開しています。そんな蜂谷さんの起業したきっかけや成功のポイントを見てみましょう。
職場復帰の難しさから起業する女性が少なくないという事実
大学を出てから、システムエンジニアとして12年間働いていました。何度か転職はしましたが、会社勤めは継続し、結婚後も働いていました。2011年には子どもを出産するために産休と育休を取り、すぐに職場復帰をしたのですが、そこで子育てをしながら仕事をすることの難しさに直面したんです。多忙な毎日を過ごす中で、「なぜこの仕事をしてるんだろう?」と、思い悩むようにもなり、すぐに会社を辞めて転職活動を始めました。でも、結果はどこも不採用。誰も雇ってくれないのであれば起業するしかないと、気持ちを切り替えました。そこで立ち上げたのが、BEEVALLEYです。
Web制作を仕事にしようとあれこれ調査していくうちに気づいたのが、自分と同じように子育てによってキャリアが中断し、職場復帰が難しくなったため起業したという人が少なくないという事実でした。ただ、起業しても稼げていない女性は多く、その原因を調べると、そもそもWebに詳しくなくてホームページを立ち上げられない、Web広告が仕掛けられないという、スタート時からつまずいている人ばかりだったんです。そこで、そうした女性向けに特化したWeb制作会社を立ち上げようと考えました。
女性が起業するなら家族に応援してもらえる根拠づくりを
私は女性の起業支援をしているので、特に女性に対してお伝えしておきたいのが、開業や独立は絶対的に家族の応援が必要だということです。家族を説得できないと起業は夢のまた夢になってしまいます。家族に理解してもらい、協力を得るためには、説得のための根拠や材料が必要で、それは徹底したリサーチと少しのアクションでしか得られません。「この商品は売れると思う」だとか、「こんなサービスが喜ばれるはず」だと、やはり家族の理解は得られないでしょう。そこで、最低限でも同様のビジネスをしている人に会いにいって、話を聞いてくる。もしくは専門家の本を読む。その情報は説得材料になります。まずは徹底的に調べ尽くすことから始めてみることをおすすめしたいですね。そしてその次に、少しだけアクションをしてみる。徹底したリサーチと少しのアクション。この繰り返しこそが、家族の説得材料になっていくと思います。
蜂谷さんのケースでは、自分自身や同じ境遇の人々の「困った」を掘り下げることによって、具体的な起業アイデアが生まれました。こうした「自分ごと」として捉えられる課題に取り組んだことが、成功のポイントとして挙げられます。また、成功に向けて「家族の応援が必要」という点は、女性に限らず男性にとっても重要な要素と言えます。
よくある起業失敗パターン
起業を成功させるためには、失敗から学びや教訓を得ることも重要です。起業失敗の典型的なパターンをご紹介します。
起業の目的が明確になっていない
起業家の失敗例として一番多いのが、このパターンと言っても過言ではありません。自分で事業を始め、継続させていくためには「強い意志」が必要です。そのために、起業目的を明確にすることが欠かせません。そもそも目的がないということは、成功の基準すらないということです。「会社が嫌だから」「仲間に誘われたから」「儲かりそうだから」といった軽い気持ちで、目的が曖昧なまま起業をしてしまうと、「起業すること」がゴールになり、短期間で失敗するケースが少なくありません。
成功体験から抜けられない
事業を立ち上げた後、一度うまくいった起業家に多いパターンです。それまで順調に進んでいた事業が停滞したときに、「前はこのやり方でうまくいっていた」という成功体験に縛られて、取引先や消費者のニーズに対応できないことがあります。過去の成功体験には自信を持ちつつも、物事の変化に柔軟に対応することが重要です。
経営者としての「見栄」を優先してしまう
「立派な会社に思われたい」という欲求から、分不相応に広いオフィスを構え、無計画に社員を増やしてしまう起業家も少なくありません。事業が好調なときほど見栄を張りたくなるものですが、家賃や人件費などの固定費が負担になり、一気に経営が行き詰まる事例もよく耳にします。特に、起業当初はスモールスタートを心がけ、固定費の支出には慎重になったほうが良いでしょう。
起業に必要な資金とは?

起業で失敗しないためには、起業資金に関する基本知識を事前に知っておくことも重要です。手続きそのものにかかる費用や、資金を要する際の調達方法などを押さえておきましょう。
起業手続きにかかる費用
起業の手続きにかかる費用は、個人事業主と法人とで異なります。「起業には潤沢な資金が必要」というイメージがあるかもしれませんが、いずれの場合も起業するだけであれば大きな費用はかかりません。特に、個人事業主の場合は税務署に開業届を提出するだけで、1円もかからずに手続きは完了します。
会社を設立する場合は、定款認証や登記などの手続きが必要となり、約6万円〜24万円の法定費用がかかります。その他、会社印や定款の作成などに3万〜5万円程度の費用がかかることを頭に入れておきましょう。現在の会社法では資本金に必要な最低額が定められていないため、法律上は1円以上の資本金があれば設立することが可能です。
【会社設立にかかる法定費用】
| 株式会社 | 合同会社 | |
| 定款印紙代 |
40,000円 ※電子定款の場合は0円 |
40,000円 ※電子定款の場合は0円 |
| 定款認証手数料 | 50,000円 | 0円 |
| 定款謄本代 | 2冊で2,000円程度 | 0円 |
| 登録免許税 |
150,000円 または資本金の額×0.7% ※いずれか大きい方 |
60,000円 または資本金の額×0.7% ※いずれか大きい方 |
| 合計 |
242,000円 ※電子定款の場合は202,000円 |
100,000円 ※電子定款の場合は60,000円 |
- ※参照:国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続援」
- ※参照:法務省「商業・法人登記申請手続」
- ※参照:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」
- ※参照:国税庁「[手続名]内国普通法人等の設立の届出」
資金調達の方法
個人事業主であれば0円、会社を設立する場合でも10万円程度で起業できますが、実際には設備や備品の準備、スタッフの採用などに費用がかかるため、プラスアルファの資金が必要です。事業の内容や規模によって金額は異なり、大きな設備やオフィスが必要な場合には、数百万円の費用がかかるケースもあります。初期費用が少なく済む場合も、事業が軌道に乗るまでの運転資金は準備しておく必要があります。
起業アイデアが固まったら事業計画書の作成を進め、具体的にどれくらいの費用がかかるのか算出し、資金計画を明確にしておきましょう。必要な資金をすべて自分で用意できない場合は、何らかの方法で資金を調達しなくてはいけません。起業に向けてしっかりと計画を立てて資金を蓄えると同時に、以下の代表的な調達方法についても事前に調べておくと良いでしょう。
日本政策金融公庫の創業融資
日本政策金融公庫は政府が100%出資している政府系金融機関です。国の政策のもと、創業支援や中小企業の事業支援を推進する役割を担っており、無担保・無保証人で利用できるさまざまな融資制度が用意されています。
民間金融機関の融資
都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合などの民間金融機関から融資を受ける方法もあります。新規事業の場合は、信用不足により銀行固有の融資(プロパー融資)を受けることが難しいため、国の機関である信用保証協会を保証人として融資を受けるケースがほとんどです。
クラウドファンディング
最近はインターネットでお金を募るクラウドファンディングも、起業時の資金調達方法の1つとして活用されています。多くの人から注目・賛同を集めることが重要なため、今までにない画期的なサービスや社会課題の解決につながるビジネスと相性が良い方法と言えます。
ベンチャーキャピタル(投資会社)
ベンチャー企業への投資を本業とするベンチャーキャピタルから出資を受ける方法もあります。株式交換で資金を得るため、返済の義務がない代わりに、会社の経営参加権を付与することになります。自らベンチャーキャピタルに売り込みにいくか、ビジネスコンテストなどに出場して高評価を得る必要がありますが、事業の将来性が見込まれれば多額の資金を調達できる可能性もあります。
利用できる助成金・補助金
企業資金の調達方法として、国や自治体などの助成金や補助金を利用する方法もあります。
助成金とは国や自治体が定める要件を満たしている場合に給付されるもので、要件を満たし、所定の手続きを行えば原則給付されます。一方、補助金は採択件数(給付件数)や金額が事前に決まっており、事業計画書などの内容審査を経て採択された場合に給付されるものです。そのため、申請しても採択されないケースもあります。
なお、助成金や補助金は融資と違って返済の必要はありません。自治体によって支援内容は異なるため、起業を検討している地域の情報を確認してみると良いでしょう。ここでは起業時に利用できる主な補助金・助成金をご紹介します。
小規模事業者持続化補助金(経済産業省)
小規模事業者(個人事業主含む)向けの補助金で、販路開拓などの取り組みに対して最高200万円が支給されます。補助金の受給のほか、経営計画の作成や販路開拓の実施時に商工会議所の指導・助言を受けることができます。
事業承継・引継ぎ補助金(経済産業省)
事業承継・引継ぎ補助金は小規模事業者(個人事業主含む)の事業承継を支援する補助金です。「経営革新事業」、「専門家活用事業」、「廃業・再チャレンジ事業」という3つの事業に分かれており、「経営革新事業」では、創業にあたって廃業予定者等から経営資源(設備、従業員、顧客等)を引き継いだ事業者を対象に、最高800万円の補助金が支給されます。
IT導入補助金(経済産業省)
小規模事業者(個人事業主含む)を対象とした補助金です。業務効率向上を目的としたITツールの導入に対して支給されます。会社設立後から申請でき、最大で450万円の補助が受けられます。
ものづくり補助金(経済産業省)
ものづくり補助金は生産性の向上に向けてサービス・試作品開発、生産プロセスの改善などに取り組む小規模事業者(個人事業主含む)を対象に、設備投資に対して支給される補助金です。通常の補助金額は100万円〜1250万円ですが、特別な要件を満たすことで補助金の上限が引き上げられることもあります。
創業助成金(東京都中小企業振興公社)
「都内で創業を予定されている人」または「都内で創業して5年未満の中小企業者等の人」を対象とした助成金です。最大で300万円が支給され、賃借料、広告費、器具備品購入費、人件費など、創業初期に必要な経費に活用できます。
キャリアアップ助成金(厚生労働省)
従業員を雇う場合に検討すべき補助金で、非正規雇用の労働者を自社内でキャリアアップさせるとき活用できます。「正社員化コース」や「賃金規定等改定コース」などの7つのコースがあり、例えば創業時にアルバイトとして雇っていた従業員を正社員に登用する場合、小規模事業者であれば最低28万5000円から最高72万円の助成が受けられます。
トライアル雇用助成金(厚生労働省)
トライアル雇用助成金は、職業経験の不足などを理由に安定的な就職が困難な求職者を一定期間(最長3カ月)試行雇用した場合に支給される助成金です。1人につき月額最大4万円が支給されます。
人材確保等支援助成金(厚生労働省)
人材確保等支援助成金は、労働環境の向上等を図る事業主等を対象とした助成金です。いくつかのコースがあり、例えば「テレワークコース」ではテレワークに必要な機器等の導入にかかった費用の30%が助成されます。
無料で相談できる起業支援機関
起業を成功させるポイントとして「人とのつながりを大切にする」を挙げたように、周りの知恵を借りることは起業成功への近道です。起業について「もう一歩踏み込んで詳しく知りたい」「不安や心配な点がある」という場合は、全国各地にある支援機関に相談することをおすすめします。無料で利用できる相談窓口をはじめ、研修やセミナーを開催している機関もあります。積極的に情報を集め、遠慮せずにサポートを受けましょう。
商工会議所
商工会議所は、商工会議法に基づいて組織される商工業者による非営利の経済団体です。全国各地の拠点に相談窓口を設け、起業の進め方や事業計画書の作成、資金調達、会社設立の手続きなど、起業に関するさまざまな相談を無料で受け付けています。起業支援セミナーや講座なども開催しています。
中小企業支援センター
中小企業支援センターは、中小企業の支援・課題解決を目的として設立された公益財団法人で、各都道府県に存在します。各地のセンターに起業・創業希望者向けの相談窓口があり、さまざまな相談に対応しているほか、セミナーや研修会なども開催しています。
日本政策金融公庫創業サポートデスク
日本政策金融公庫では融資相談だけでなく、全国の支店に創業サポートデスクを設置し、創業に関する相談も幅広く受け付けています。無料・予約不要で、創業支援の専任スタッフによるアドバイス・サポートを受けることができます。
マイナビ独立エージェントサービス
「マイナビ独立エージェントサービス」では、専任のアドバイザーが独立・開業に関する悩みや不安をヒアリングし、1人ひとりに合ったアドバイスを行っています。希望する方は「独立開業分野の適性診断」を受けることも可能です。マイナビへの来社が難しい場合には、お電話でのご相談も受け付けています。
起業成功に関するまとめ
ここまで、起業を成功させるためのポイントをはじめ、起業アイデアの見つけ方、身近な起業家の成功事例、よくある起業失敗パターン、起業資金に関する情報などをご紹介しました。
「起業家として成功するためには、斬新なアイデアや特別なスキル・能力が必要なのではないか」と考えている方も多いと思いますが、決してそんなことはありません。ここでご紹介したポイントや情報を参考に、リスクの少ない方法で起業すれば失敗する確率は軽減できます。起業に関してわからない点があれば、無料で起業相談ができる支援機関も有効に活用しながら、理解を深めていきましょう!一人で起業することが不安な方は、フランチャイズの加盟店や代理店として起業する方法もあります。自分に合った方法で、ぜひ起業を成功させてください。
■関連記事
起業のメリット・デメリットとは?知っておくべきお金の知識も紹介
業務委託とはどんな働き方なのか?フリーランスとの違いやメリット・デメリット、注意すべきポイントとは?
代理店とは?仕組みや種類、代理店として働くメリット、選定方法など押さえておきたい基礎知識
なぜあの人は起業に失敗するのか。失敗する要因と、8つの対策を詳しく解説
フランチャイズ契約とは?知っておくべきフランチャイズ契約の基礎知識と注意すべきポイント